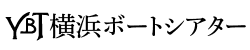薄れゆく時代の記憶と、今とをつなぐ〈艀〉

映画とトークで再発見する現代日本、そして艀の歴史
〈艀〉を舞台にした映画「泥の河」を、艀の劇場(船劇場)で上映。戦後の苦難から高度経済成長、現代に至るまでの日本の歴史を、艀、川、そして映画という切り口で、三人の専門家が熱く語ります。
泥の河
時代を描いた少年ドラマの傑作

作品紹介
自主製作、自主公開という小さな取り組みから始まった本作は、欧米はもとより、旧ソ連邦、中国やアジア諸国にまでその配給をひろげて、今日でも名作として語り継がれている小栗康平監督のデビュー作。 宮本輝の処女作を原作に、少年少女たちのひと夏の出会いと別れが切々と描かれる。
あらすじ
日本が高度成長期を迎えようとしていた昭和31年。大阪・安治川の河口で食堂を営む板倉晋平の息子・信雄は、ある日、対岸に繋がれているみすぼらしい船に住む姉弟と知り合う。だが信雄は、その船には夜近づかないようにと父から言われていた…
スタッフ/キャスト
製作:木村元保
原作:宮本輝
脚本:重森孝子
監督:小栗康平
撮影:安藤庄平
照明:島田忠昭
美術:内藤 昭
音楽:毛利蔵人
出演:田村高廣、藤田弓子、加賀まりこ、殿山泰司、蟹江敬三、芦屋雁之助 他
主な受賞
キネマ旬報ベストテン第1位
日本映画ペンクラブ第1位
キネマ旬報日本映画監督賞
毎日映画コンクール最優秀作品賞・最優秀監督賞
ブルーリボン最優秀作品賞
日本アカデミー賞最優秀作品賞
文化庁優秀映画賞
モスクワ映画祭銀賞
アメリカアカデミー賞外国語映画部門ノミネート
日本映画監督協会新人奨励賞
芸術選奨文部大臣新人賞
毎日映画コンクール主演男優賞:田村高廣
キネマ旬報助演女優賞:加賀まりこ
開催概要
- イントロダクション(10分)
-
上映に先立ち、作品の時代背景や当時の時代感覚について歴史家が語ります。
- 映画『泥の河』上映
-
上映時間:105分/製作:1981年/日本映画/モノクロ/16ミリフィルム上映
- アフタートーク(40分)
-
- 「舞台装置としての艀と川」松本和樹
- 日常の中の異質なもの〈艀〉。なぜ艀や川が、文化運動において時代を描く舞台装置として取り上げられたのか。作品ゆかりの地の取材報告と共に。
- 「時代を識る。今を観る。映画は存在の羅針盤。」河北直治
- 作品に見る時代の重層性を読み解いてみたい。今という価値観と、時代の空気を、綯い交ぜにする絶好の機会だと思う。
- 「映画はなぜ、時代の空気を映し出せるのか?」古澤敏文
- 元映画プロデューサーが語る、映画という媒体の可能性と魅力について。
※アフタートークは異なる内容を2日間に分けて語ります。
- 「舞台装置としての艀と川」松本和樹
トーク登壇者
松本和樹(横浜都市発展記念館調査研究員)
1987年生まれ。博士(歴史民俗資料学)。専門は日本近現代史。仲仕や艀など、港で荷物を運んだ人びとの生活・労働に注目して近現代史を分析している。最近の業績に、「運河で生きる~都市を支えた横浜の“河川運河”~」(横浜都市発展記念館2024年度企画展示)、「川の町・横浜の姿 ―横浜市街地の河川運河と水運―」(平山昇編『大学的神奈川ガイド こだわりの歩き方』株式会社昭和堂、2024年10月)。
河北直治(横浜運河史研究家・横濱界隈研究家)
1953年東京生まれ。西区在住。路上観察学会世話人、大岡川運河周辺史を研究。濱橋会歴史部会。路上観察・運河ガイドを通して横浜を新しい視点で捉える作業をしている。季刊横濱57号「特集 大岡川をめぐる物語」、「横浜・川崎・鎌倉凸凹地図」(昭文社)共同執筆、大岡川運河ガイドブック(よこはま都心部水上交通実行委員会)運河ガイド・地域まち歩きはそれぞれ100回を超える。
古澤敏文(元映画プロデューサー、今は自由人)
1958年生まれ。北京電影学院客員教授、元東京芸術大学非常勤講師。1979年制作の「狂い咲きサンダーロード」から映画に携わり、以降プロデューサーとして多くの映画や番組を制作する。映画「白痴」はベネチア国際映画祭で第一回デジタル賞を受賞。また、障害者施設支援や地域活性に取り組んでおり、映画『The Spirit of Yokohama』は映画制作と地域活動の経験を活かして制作する。
開催日時
- 2025年 5月16日(金) 18:30開演(21:30終演予定)
- 2025年 5月17日(土) 17:00開演(20:00終演予定)
※開場は30分前
※途中15分休憩あり
開演40分前に、横浜人形の家2階入口前集合(みなとみらい線「元町・中華街駅」徒歩2分)。
案内の者が会場までご案内いたします。
会場
横浜ボートシアター 船劇場
参加費
2500円・要事前予約
予約・お問い合わせ先(横浜ボートシアター)
その他のご予約方法
080-6737-5208
※メールでご予約の場合、下記情報をご記載いただけますとスムーズです。
・参加人数
・代表者氏名
・メールアドレス
・お電話番号
・ご希望のお支払い方法(郵便振替、横浜銀行、PayPalのいずれか)
艀とは
艀は箱型をした自走できない船です。タグボートに引かれ沖から陸地へ荷物を運搬するこの船は、大型船の入港が困難な横浜には不可欠な存在でしたが、コンテナの発達で数が急減しました。昭和後期から平成初期までは、第一線を退き河川に停泊した艀の独特な空間がブティックや劇場等に転用されました。横浜のディープな景観を描き出す艀群のアップサイクルは、大きな可能性を秘めています。
シリーズ つなぐ〈艀〉とは
船劇場を市民に開かれた場にしてゆく取り組みの一環として、歴史研究者である河北氏と松本氏と共に企画し、2024年10月に開始。船劇場の母体である「艀」の存在を切り口に港や横浜、日本の歴史を紐解くシリーズです。
第一回は、子供達の残した作文を題材に、横浜港発展の歴史と、艀で働き居住していた労働者とその家族たちの生活の実態に迫りました。
◆横浜ボートシアタープロフィール
横浜元町を流れる中村川に係留した木造はしけを船劇場に改造、拠点とし、1981年より活動を開始。“アジア”をテーマに仮面や人形、手作り楽器などを用い、語りや舞踊的身体表現、緻密な音楽表現を軸に叙事詩を物語る祝祭劇を展開。波に揺れる赤錆びた船劇場の非日常空間は荒々しいエネルギーを持っており、その場ならではの力強い作品の創造を可能にしてきた。
2020年に前代表の遠藤啄郎死去に伴い、劇団は若手中心の新たな体制となり、集団創作による作品発表を開始。船劇場を「市民も活用できる開かれた劇場に」という新たな方針を打ち出し、横浜の市民とともに劇場を支えていく枠組み作りと、国際的な文化拠点への成長を目指している。
イベントスタッフ
チラシデザイン・音響:松本利洋
舞台:吉岡紗矢、奥本聡
映写:古澤敏文
主催:横浜ボートシアター
協力:映画『The Spirit of Yokohama』、NPO法人 HamaBridge 濱橋会、木霊の会、「みんなの山下ふ頭に〇〇があったらイイナ」プロジェクト、YOUR Social Project、Yokohama TUG Culture Club.、横浜舞台表現研究会、横浜ボートシアターを目撃する会、YOKOHAMA路上観察学会