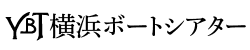舞台が始まりすぐ、語り部の台詞も含め、脚本のほとんどの言葉が石原の詩と散文からなっていることに気づきましたが、それでいながら、全体が確固たる劇として成立していることに、上演中からすでに、率直に感銘を受けました。このようなことが可能な日本の現代詩人は、けっして多くはないはずだと。とくに「難解」と言われることの多い石原の詩句が、舞台上でこんなにも力強く響いているのを聞きながら、彼の言葉の真正さというものを再確認する思いでした。
詩と演劇、とくに物語を持たない抒情詩と演劇との関係については、以前にも時折考えるときがありました。詩が本来は歌われるものであった以上、それは舞台上で、何らかの所作と共に「演じ」られるべきものなのかもしれないとも思いましたし、石原の後期の詩で、演劇的なジェスチャーのシナリオのようなものがあるのも気になっていました。
詩と舞台ということで言えば、詩の朗読の重要性、詩に身体性を取り戻さなければならない、といったことが、以前からずっと言われてきましたが、本公演に接して感じたのは、そのような(伝統的な)朗読の形ですら、詩にとっては不十分だったということです。一人の個人による朗読という形態は、詩を「個人の表現」とみなす考えに縛られているように思います。この「個人」には「特別な、独創的な……」という意味合いが暗に含まれています。しかし、石原の詩は、けっしてそのような意味での「個人」の表現ではなかったのです。
「サンチョ・パンサの帰郷」本編01:07:30〜

例えば、今回の舞台でも読まれた「サンチョ・パンサの帰郷」は、石原の詩の中でもとりわけ難解なものとして知られていますが、その「難解」さの原因は、おもにこの詩の中に複数の声が響いている(複数の声の主がいる)ということにあります。詳細は省きますが、よくよく検討してみると実際にそうなのです(詩末尾の「何ものものこしてはならぬ」が二度繰り返されるところを考えてみるだけでもよいでしょう)。ですから、本公演でのように複数の人による掛け合いで朗読された場合、この詩はそのまま自然に受け入れられるようになります。このことに気づかせてもらったのは、とても大きな収穫でした。
劇中では石原の一篇の詩を、収容所での支配する側と支配される側の双方が、互いに引き取りあいながら朗読するところもあり、非常に面白く思いました。確かに石原の詩の言葉は、けっして支配される側の位置のみから発せられるものではなく、それは支配する側とされる側との「間」で響いているように思われます。その意味でも、詩の声は「複数的」になっているわけです。
「位置」本編01:14:18〜

このような、支配する側/される側というような単純な図式に回収されない、自分固有の立つ位置というものを、石原は独自の意味で「位置」と呼び、同名の詩篇「位置」が彼の代表作とされていて、本作でも朗読されていましたが、考えてみれば、演劇では舞台上での立つ「位置」というのが絶対的に重要になる以上、この「位置」という概念もすぐれて演劇的であるように思います。しかし、その「位置」がかけがえのない、固有なものであればあるほど、そこから発せられる声は、逆説的にも複数的なものになるのです。
本公演では「いちごつぶしの歌」を始めとして、いくつかの石原の詩に曲がつけられていました。実際、彼の詩には様々なジャンルのメロディが想定されているようなもの、俗謡や何かの替え歌かと思えるようなものも多く、彼の詩作の一つの個性をなしていると言えますが、ここにも広い意味での「声の複数性」を見てとってもよいかと思われます(他人の声のうえに自分の声をのせる、というような)。公演中では、詩「麦」がコラール風の旋律の合唱で歌われていましたが、実際、プロテスタントのキリスト者であった石原の詩の一つの基盤として、賛美歌の調子があったことは確かです。彼の詩のそうした面が引き出されていたという点でも、彼の詩を舞台化する大きな意味があったと思います。
「麦」本編01:16:50〜

ちなみに、本舞台では様々な音楽的要素が散りばめられており、やはりそれが楽しく感じられました。影絵のところではガムラン風の音楽が聞こえ、また、浄瑠璃を模していると思われる箇所は、大変聴きごたえがありました。こうしたところに遠藤啄郎さんの遺産が受け継がれているのかなと想像しました。
「さびしいといま」本編00:55:45〜

「さ・び・し・い」という文字の影絵による詩「さびしいといま」の場面は、見どころの一つだったと思います。ふと漏らされた「さびしい」という声がそばで聞こえたような気がする、というのが、この詩で暗に言われていることですが、それが次第に「さびしい」という文字の形をとってゆく影絵の成りゆきと対応しています。つまり、ここでもスクリーン上に(沈黙のうちに)響いているのは声なのであり、しかもそれは伝統的(近代的?)な朗読におけるような「個人」の声ではないのです。こうした、主のさだかでない声というのもまた、石原の詩に特徴的なものであると思います。
「その朝サマルカンドでは」本編00:08:40〜

また、それに先行する場面では、影絵のスクリーンには主に役者さんたちの影が映されていたことを考えるなら、そうした人間の身体がとる姿形も、それ自体(詩の)文字であり、声なのだと考えることも可能です。そして、それを伏線とすると、劇の末尾でスクリーンに映し出される詩「土地」のテキストも、一つの影絵なのだと見なすことができるような気がします。これまで圧倒的な力で舞台上に響いてきた石原の言葉はすべて沈黙しますが、この不意に訪れた時間の中、観客はこの「テキスト=影絵」を追いながら、他の観客一人一人の心の中でも、今これらの言葉が確実に「響いて」いるはずだという得難い体験をすることになるのです。
(ところで、『白い影絵』というタイトルは、構想当初からの遠藤啄郎さんによる発案だということですが、この言葉自体、大変興味深いものです。光を遮る物体の物質性が影絵を成り立たせているのだとすれば、「白い影絵」とは、その物質性自体が光と化すということになるかと思います。一つ考えられるのは、物質性を有する人間の身体が発する声=言葉が光なのだということですが、どうでしょうか……)
このように、本公演では、言葉、文字のうちに結晶化された石原の「詩」というものが、非常にストレートに舞台化――身体化、音響化、影像化……されているように感じました。そこから観客一人一人は、今度は自分自身のための石原の詩句を選びとってゆくのではないでしょうか。このような形での詩への導きがありうるということは、私にはまったく思いがけないことでした。
その後、遠藤啄郎さんが1974年、まだ石原吉郎の存命中に、彼の詩から着想を得て創作された「夕やけぐるみの歌」の記録映像を拝見しました。詩のほうも、劇のほうも、民話「かちかち山」をそれぞれの仕方で語るもので、劇のほうには石原の詩の集団的朗読、歌謡化が部分的に行なわれていますが、それ以外は、両者の関わりは薄いように見えます。しかし、私自身は、石原の詩がやはりこの演劇作品の出発点なのだろうなと納得できました。
『夕焼けぐるみの歌』1987年 森の劇場

石原の詩「ゆうやけぐるみのうた」は、「かちかち山」の物語を悪辣な俗謡に仕立てているという点で、ちょっと特異なものですが、さらに重要なのは、狸の背中に燃える火を「夕やけ」に見立て、海に沈みゆくそれを水平線上の夕陽と重ねることで、物語を宇宙規模の神話にしてしまっていることです。壮大な神話がそのまま一つの「うた」に収まっているという、この石原の詩のあり方が、遠藤さんが創出した、あの凄まじい儀礼空間の核にあることは、ほぼ確かであるように思われます。
そこで思うのは、石原はどこかで海に沈む夕陽を見たのだろうかということです。日本では夕陽が沈むのは日本海になりますが、石原はもしかしたら帰国時の船上でそれを見たのではないでしょうか。エッセイ「望郷と海」の末尾には、石原らを乗せた興安丸は1953年12月1日朝にナホトカを出港、同日夜に舞鶴に入港とあります。もちろんこれは仮説にすぎません。しかし、このように考えるなら、太平洋戦争後の日本で行き場を失っていた「荒魂」の鎮魂として劇「夕やけぐるみの歌」が作られたという事実に納得がゆくのです。
最後に取り組まれた劇作で遠藤さんが再び石原吉郎に戻られ、残された方々がそれを完成されたということに、何か運命的なものを感じてしまいます。演劇の場合、最終的に上演される舞台だけでなく、その創作過程そのものが芸術行為であるという側面がとくに強いように思いますが、石原吉郎の詩業に対し、このような本気の応答がなされているということを(構想は一年に及んだと伺っています)、大変心強く思いました。『白い影絵』の再演を切に願っております。今日の状況がそれを必要としているように思われるのです……
斉藤毅(さいとう・たけし)
大妻女子大学他、非常勤講師。専門はロシア文学・文化。共著に『他者のトポロジー――人文諸学と他者論の現在』(書肆心水)他。 訳書にマンデリシターム『言葉と文化――ポエジーをめぐって』(水声社)他。